【熟年バンザイ!】なぜこの歳で合氣道なのか?入門以来1年半、私にとって合気道は、生活に不可欠な時間。
2011年12月4日投稿|中高年の楽しい合氣道 中野道場
(1)「なぜその年で合氣道なんだよ?」
たいがいの中高年はそう思いますよね。なにが面白くてさ・・と。
周囲のそんな声をよそに楽心館の門をたたいたのは、還暦目前の昨年春。
健康のためとか、体力づくり、護身のため・・なんてことは考えず、(何となく、合氣道が気になっていて・・)という、説得力のないノーテンキな動機でした(むろん、時間が多少自由になったことがある)。今から思えば、(何となく気にかかる)というある種の感覚は間違っていなかったと思う。
さすがに、この髪の薄い前記高齢者を前にすると、普通の道場は、(稽古中に脳卒中でも起こされては困る)と腰を引いてしまうらしく、「シニアや女性の入門も歓迎する道場」の噂を頼りに、おそるおそる楽心館中野道場の稽古をのぞかせていただいたのがきっかけでした。
稽古はさぞやバタンバタン投げ飛ばされているかと思いきや…私同様、還暦から始めて黒帯になったという先達や女性もいて、予想よりは粛々として穏やかな稽古風景を拝見。これなら私も足手まといにならずについていけるかな…と目を瞑り、清水の舞台から飛び降りたしだい。
とはいえ、酒・タバコにきっちり「律儀」を通してきた私の体は、当初、受身ででんぐり返っただけで目の前に星がちらつく状態からのスタートでした。
それでもどうにかこうにか慣れるものですね。以来1年半、私にとって合氣道は、生活に不可欠な時間といっても過言ではありません。理由は三つあります。
一つ目:「師を持つことの喜び」
当たり前ですが、実社会ではたいがい教導する側に立たされる中高年には新鮮なマインドセットになります。稽古の間はひたすら先生の指導に自分を預け、頭を空っぽにしてついていくのみ。小学生が先生の話を白紙のアタマに刻んでいくのと変わりありません。
むしろ、この歳だからこそ、頭を空っぽにできる貴重な時間です。
二つ目:「身体で考える時間を創れること」
情報過多の世の中では、どうしても頭ばかりが優位になり、身体の声を聞く力が鈍っていきます。稽古を通してまず気づくのは、自分が思っている体の動きと、実際の動きとのズレ。
「あれ?」の連続の中で、楽器のチューニングのように自分を整えていく時間。それが稽古です。稽古後のビールのうまさもまた格別!
三つ目:「合氣道は人間関係そのものだった」
一番大きいのはここです。合氣道の原理は、単に技をかけるための身体操作ではなく、「相手とつながる術」であり、「人の心を動かす技」だと気づきました。
人生経験豊富な中高年こそ、この術理に共感できると思います。今までの人間関係のつまずきも、「つながり方」を知らなかっただけだと気づける。
日常会話や家族、友人関係、仕事場においても、「合氣道的なつながり」があれば、感情的なぶつかりも減り、深い理解が得られるのではないでしょうか。
言葉もまた身体の一部です。同期・共鳴して初めて人に伝わるものだと、合氣道は教えてくれます。
まとめ:「この歳だからこそ合氣道」
若い頃には気づけなかった「つながる」ことの意味を、今、体で学んでいます。
「なぜその歳で合氣道なんだよ?」という問いに、私は胸を張ってこう答えたい。
「この歳だからこそ、合氣道なんだ」と。
今後もこのブログでは、熟年世代から見る合氣道の妙味を、具体的に書いていきたいと思います。
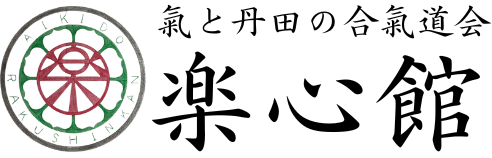
到らぬ自分で (石川です)
2011-12-29 22:31:14
一つは、「師を持つことの喜び」です。
二つ目は、「身体で考える時間を創れる」こと。
三つ目は、一言で言えば、(人間関係を術理として身につけ、相手の心を動かす技)であり。
明確な目的意識をお持ちで、良く理解できました。
どうにも三つ目は、当方がお教えいただきたいです。
到らぬ自分です。
省みて
己に羞じよ
為す技の
言の葉に
つゆも似ぬ身を