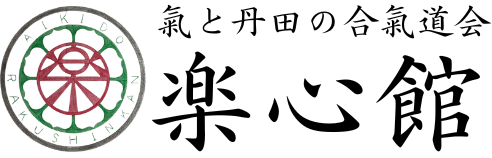小学1年生が教えてくれた「準備の大切さ」
とある小学1年生の生徒が、稽古場にやってきました。
彼女は審査の技を「スノボみたいに体が覚えちゃった!」と自信満々に話していました。でも、以前の審査会では技の手順が分からなくなり、頭が真っ白になって立ち尽くしてしまったことがありました。
その日の稽古では、その出来事を振り返りながら、彼女と1対1で稽古をしました。
稽古の中で技をやらせてみると、また同じように立ち止まってしまいました。手が震え、帯をいじりながら泣き出してしまいます。私は叱るのではなく、 「自分が今どういう状況にいるか」 を彼女自身に気づかせることが大切だと感じました。
彼女が技を止まってしまう原因は、技の流れを完全に理解しないまま「なんとなく」動いていたことにありました。
稽古では受け(相手役)が協力してくれると、少しの理解不足でも技が成立してしまいます。
しかし、自分の中にしっかりとした準備や理解がないと、相手が協力しない場合にどう動いていいか分からなくなってしまうのです。
「準備をすること」の感覚が薄い現代の子どもたち
実はこの話、学校での学び方にも通じる部分があります。
最近の小学校のテストでは、授業で学んだ内容そのままが出題されることが多く、授業中にしっかりと聞いていれば簡単に100点が取れるようになっています。そのため、子どもたちが「自分で準備をして挑む」という経験を積む機会が少なくなっていると感じます。
例えば、この生徒も学校のテストではいつも100点を取っているそうですが、それは授業内で準備が完結しているからこそ。 「自分で準備をしっかりしている」 という自覚を持つことが少なく、いざ自分で準備を整えなければならない場面に直面すると、戸惑ってしまうことがあります。
今回の合気道の稽古でも同じことが起きました。授業の延長のように「なんとなく」動いていただけでは、技を止まらずに進めることはできなかったのです。
「自分で気づく力」を育てる稽古
稽古の中で、彼女に4つの技をランダムにやってもらいました。途中で立ち止まってしまう場面があり、すでに4つ終わっているのに「まだ3つしかやっていない」と思い込んでしまいました。それでも声をかけながらヒントを出し、最後までやり切らせました。
最後にもう一度課題の技をやらせると、なんとか止まらずに動き切りましたが、動きには明らかに自信のある技とそうでない技の差が見えました。終わった後に話を聞いてみると、彼女は初めてこう答えました。
「1つ目と2つ目の技が自信がない」
ここで、彼女は自分がどこでつまずいているのかを初めて自覚しました。
この 「自分で気づく力」 が育つことこそ、稽古の大きな成果です。
自分が準備できていない部分を見つけ、それにどう向き合うかを考える力が、成長のきっかけになります。
準備が成功を生むということ
私は彼女にこう伝えました。
「どんなことでも、しっかり準備をすればうまくいくよ。準備ができていれば怖くないんだ。」
合気道の稽古を通じて、技を覚えるだけでなく、「準備をすることの大切さ」を学んでほしいと思っています。
学校のテストのように、授業の中だけで準備が完了する環境とは違い、道場では自分で工夫して準備を進める力が必要です。この経験は、将来どんな場面でも活きてくるはずです。
学び:自信は準備から生まれる
この稽古から私自身も学んだことがあります。それは、子どもたちが自信を持つためには、以下のことが必要だということです。
1. 準備を「自分の力で進める」経験を増やす
学校や習い事でも、誰かが与えてくれる準備ではなく、自分で計画して進める経験を意識的に増やすことが大切です。
2. 自分の現状を自覚する時間を作る
失敗を恐れずに、今の自分が何を理解していて、何が分からないのかを振り返る機会を与えると、子どもは自分で気づき、成長していきます。
3. 成功体験を積み重ねる
最初から完璧を求めるのではなく、小さな準備や練習を繰り返しながら成功体験を積むことで、自信がついていきます。
まとめ:合気道で学ぶ「準備の力」
今回の稽古で、小学1年生の生徒は「準備の大切さ」に少しずつ気づき始めました。
技を止まらずにできるようになるためには、自分で準備を進め、理解を深める必要があります。そしてその準備は、合気道だけでなく、人生のどんな場面でも役に立つ力になります。
この記事を読んでいる親御さんや指導者の方にも、ぜひお子さんが「準備」をする時間を見守り、その中で成長する姿を感じてほしいと思います。
準備ができた時、子どもたちはきっと自信を持って新しい挑戦に立ち向かうことができるはずです!