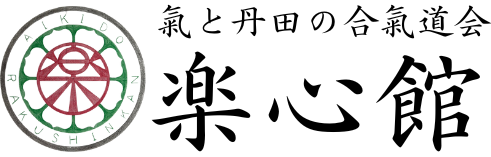合気道で(接触)(接点)の使い方が課題であるのは、いわずもがな、ですね。
実は、ある分野で、「接触」について大いに考えさせられました。
年齢的に親の介護に直面している熟年世代もいらっしゃることでしょう。
ある分野とは、認知症の人の介護です。
先頃、テレビの特集番組で「ユマニチュード」という、フランスで開発された認知症ケアの様子を見て驚きました。
ユマニチュード、直訳すると(人間らしさ)。人間らしさの尊重を意味します。
(見つめて)(話しかけ)(触れる)を柱としたケアです。
患者に優しく触れているだけで、それまで家族の顔も忘れ、医者でさえコミュニケーションを拒否していた患者が、次々と劇的に改善していくのです!
ケアを受け容れ、家族の顔も思いだし、笑顔でピースサインをするに至っては・・???!!!
(手当て)という言葉を思い出しました。
(痛いの痛いの飛んで行け~!)と、泣く子供の肌をさすっていると痛みが引いていく、あれもそうです。
近代医療以前は、病んだ人に(触れて癒す)行為は、原理はわからずとも、その効果は世界中でよく知られていたのです。
認知症はいまだ本格的な治療薬も見出されていませんが、
長寿社会の当世、年老いた親が、さっき済ませた食事も、(まだ食べてない)と記憶を失ったり、子供の顔すらわからなくなったり・・呆けるケースはごく身近な問題です。
家族がつい怒鳴りつけたり、無理やり食べさせたり、風呂に入れたり・・不本意な介護になり、家族が過労から共倒れになることもままあります。
認知症になると、本人の知覚や記憶が一体どのように変容するのでしょう。
研究では、認知症の人の視野は、前方に紙を筒状に丸めてのぞいたくらい狭い世界に狭窄するそうです。
聴覚も横や後方から声をかけても聞こえないといいます。知覚全体が萎縮するんですね。
ですから、従来の介護手法では、介護者が近づくのも気づかず、患者自身は、手を掴まれるだけで、怯えてしまうのです。
(見る)(話す)(触れる)のメソッドからなるユマニチュードでは、
介護者は、患者の狭い視野の正面からゆっくり近づき、同じ目の高さでアイコンタクトし、患者の安心感を確かめながら(語りかけ)、(触れる)段階へ進みます。
話しかける時も、「はい、手を挙げて下さい」患者の目から反応を確かめ・・「背中吹きますね」、「ありがとう」という具合。
視線も言葉も、接点が途切れないようにメッセージを送ります。
(触れる)段階では、広い面積で赤ちゃんに触れるように優しく触れます。
力を入れない、加速しない。
患者が安心感を感じられるようになれば、徐々にメッセージが通じていくといいます。
(あなたを尊重していますよ)
信頼感がつながれば、ポジティブな記憶が甦るようになります。
(目で接触し)(言葉で接触し)(優しく触れる)
接点が柔らかく密着し、切れないことが術理なんですね。
「気の通し」同様、コミュニケーションが回復するのでしょう。
ケアしていた開発者のフランス人が、合気道の達人のように見えました。
皮膚に(触れる)行為は、人が生まれてから、母親にだっこされたり、おんぶされたり、肌の接触によって、身体レベル、情動レベル、認知レベルで愛着感や信頼感を獲得していく深い世界です。
皮膚コミュニケーションともいえます。
スキンシップが希薄になった現代、触覚が秘めた深い世界は、とても重要になる気がします。
日頃から、合気道で、(接触)を通してつながることの「妙」をご存じのみなさんも、いつか直面するかもしれない、もう一つの(接触)。
目や言葉でも合気が掛かる、というのも(あり)。
(愛気道)・・ですね。