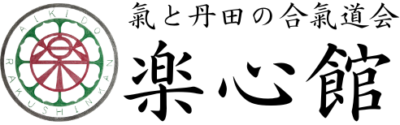無駄な時間の中にしか、確かなものは現れない
目に見えるものの“裏側”で、いつも考えていること
合氣道の道場を運営していると、営業の電話やメッセージが頻繁に届く。
「集客の仕組みを整えます」
「SNSの自動化を代行します」
「補助金を使って広告展開が可能です」――
話は丁寧で、提案も理にかなっている。
でも、実際に契約に至ることはほとんどない。
話を聞けば聞くほど、「ああ、それ、自分でやればいいな」と思ってしまうのだ。
このホームページも、自分で作った。
ブログも、稽古写真も、動画編集も、すべて自分で更新している。
少しずつ学びながら、少しずつ形にしている。
だからなのか、「50万円でやります」「100万円で組めます」と聞かされると、
どこかにズレを感じてしまう。
そうか、と思う。
“サービス”とは、思考や手間をお金で回避するための仕組みなのだ。
合氣道の稽古は、あまりにも“回り道”だ
もちろん、現代社会においては“効率”が正義だ。
時間は有限で、成果はスピードを求められる。
「何をやるか」より「いかに早くできるか」の方が評価される空気すらある。
でも、合氣道の稽古はその真逆にある。
すぐに技が身につくことはない。
形を繰り返しても、意味がわからないまま過ぎていく日もある。
何年やっても、ふとした瞬間に「何もわかっていなかった」と思い知らされる。
それでも、人は少しずつ変わっていく。
それは、段位でも技術でもない。
呼吸を合わせること、相手の重さを受け止めること、
失敗を笑えること、他人の痛みに応じようとすること――
そういった“身体の態度”が、静かに育っていく。
子どもたちとの稽古に、私は何を見ているのか
最近では、子どもたちにもあえて難しい技をやらせてみる。
説明はせずに、ただ投げてみる。
「こうすればいいよ」と言わずに、見て、感じてもらう。
すると、ある子は考え始め、
ある子は他の子の動きを見て真似をする。
そしてある瞬間、ふっと「わかったかもしれない」と小さく言う。
それは、私が教えたことではない。
その子の身体が、自分でつかんだことだ。
技術よりも、その瞬間に宿る「感覚」の方がずっと尊いと感じる。
それはたぶん、教えることでは到達できない領域だ。
この稽古は、誰のためなのか?
ときどき思う。
この稽古は、いったい誰のためにあるのだろう?
子どもたちに教えていても、すぐに分かってもらえることなんてほとんどない。
ふざけていたり、投げやりだったり、眠そうだったり――
そんな日が大半だ。
それでも私は、毎週同じように道場を開き、問いかけを続けている。
その時間に、明確なゴールはない。
むしろ、この道には終わりがないのだと思う。
だけど、たった一度だけ、ある子が自分から質問をしてきた。
別の子が、相手の痛みに気づいて手加減をした。
技がかかって「いま、なにかが通った」と感じられる瞬間があった。
それらは、成果ではない。
でも、“確かに何かが通じ合った”という手応えだけが、私の支えになっている。
無駄に見える時間の中でしか、得られないものがある
時間をかけることでしか伝わらないものがある。
失敗を繰り返すことでしか育たない感受性がある。
相手と向き合い続けることでしか生まれない信頼がある。
それらは、たいてい「効率化されない」。
むしろ邪魔だとされ、削られていくものかもしれない。
でも、それでも私は信じている。
稽古を通して、少しずつ育まれていくものの中にこそ、
この社会の中で忘れられそうな、
人間らしさの“根”があるのではないかと。
合氣道が強くするのは、技ではない
合氣道が強くするのは、技術ではなく、
**「答えの出ない問いと一緒に生きていく力」**だと思っている。
すぐにわかるものだけが価値なのではなく、
時間をかけてしか感じられないものが、確かにある。
そして最後に、なぜ私はこの不器用で報われにくい稽古をいまも続けているのか。
その答えは、こうなのかもしれない。
人は、人でしか変えられない。
そして、人が人と向き合う時間だけが、本当の教育を生む。
これは、かつて私が勤務していた赤十字病院の理念でもある。
「人間は人間でしか救えない」――
医療の現場でその言葉の重みを感じていた私は、
いま、道場という場で、また同じことを体感しているのかもしれない。