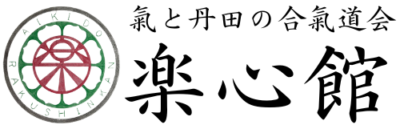剣道・鍼灸・東洋医学から合気道へ──氣への探究心
楽心館との出会いと合氣道への関心
楽心館に入門して12年目になります。合気道に興味を持ったのは今からから20年前だったと思います。
子供の頃から剣道の修行をしてきたので、合気道での“氣”をけじめとして剣道教士七段を頂いたら学んでみようと常々思っていました。
仕事でも鍼灸の治療院を開業していたことや東洋医学の鍼灸も気の調整、そして気の客観化ということでの研究に興味がありました。
そのような動機で”気“についてはご縁があり、大東流合気柔術、剣道、東洋医学での気について興味深かったことも大きな理由でした。
合気の体験と、師との縁から考察が始まる
の度、楽心館の石川先生から剣道誌を渡され「剣道の合気についての考えを聞かせて下さい。」と、“剣道時代”2019年のバックナンバーでの剣道の合気という特集の本を拝読しました。
その剣道雑誌には偶然に2年前に他界された師匠の記事が掲載されていて、その内容を拝読にさせて頂く機会に恵まれ懐かしく思えました。
そしてこれも偶然、何かのご縁であると思い、剣道における合気について自分なりの見解を述べさせて頂きます。
楽心館で学んできた「合気」の自分の理解とは「剣の理法」により支点、力点、作用点などの多面的な三角の意識を持って、
自分の体の中で練った力を相手に如何にぶつからないように効率よく伝え、相手の関節、特に肩関節を抜いて、体軸を崩すことにあると思います。
そのために構えである三次元の軸の確立することが前提です。
そして合気については、柔、力抜などが習得できて「合気」を使うことが可能となると考え、毎週、稽古の中で石川先生に指導して頂いていることです。
剣道における合気──三殺法から読み解く本質
次に「剣道における合気」とは、“剣道紙”で剣道の高名な先生方がそれぞれ執筆されている内容が剣道における「合気」の解釈だと思います。
剣道ではよく聞かれる言葉ですが**「三殺法」という教えがあります。
それは「剣を殺し、技を殺し、気を殺す」ということですが、試合では、スピード、パワー、フェイントなどで攻めても打突して有効打突**の条件があれば1本になります。
※有効打突
1.充実した気勢
2.適正な姿勢
3.竹刀の打突部
4.有効打突部位
5.刃筋正しい打突
6.残心あるもの
しかし、高段位の昇段審査では「合気になっているか?」そしてこの「三殺法」を含めて合気で相手を如何に心や身体、構えを崩しているか?というところを審査されているようです。
特に先の先、居着いたところの打突、後の先、対の先、出端の打突が審査員の先生方に心に響き、合気になった打突と評価されると思います。
構えで感じる気構え、そこには「上虚下実」で臍下の丹田に意識を持ち、足構えはしっかりと居着かない構えで、
柔らかい竹刀の剣先で中心を攻め合いながら互いの心気を感じ、攻防を行うことが剣道でいう合気だと思います。
気で崩すということ──体験と実感から生まれた理解
先ほど、師匠の話を書かせて頂きましたが、15年ほど前に剣道七段の審査を受験しているときに審査は「気で相手を攻め崩すことだ!」と言われていました。
当時は「気で崩す?」と全く理解できませんでしたが、毎回の稽古で「気で崩す」という意識を持って稽古をしていると、
日本剣道形の表現で打太刀の初太刀は機をみてという言葉があるように、その**「機」とは相手の心と体、術の変わり際におこる「きざし」**ということが理解できてきます。
例えば、高段者でも合気になっていない方と稽古をしても気の攻め合いがない稽古では、ただ「打った、打たれた」というレベルの低い稽古になってしまいます。
剣道の合気も合気柔術と同様に非常に重要な概念ですが、剣道では特に**「気を合わせる」「相手と調和する」ことに重点が置かれています。
剣道における合気は、力を使わず、相手の動きに対して無理なく反応し、自分の動きと相手の動きが一体となることで洞察力を養い、より効果的に打突を決める**ことが剣道でいう合気に繋がると思います。
剣道と合気道──二つの合気を結ぶもの
具体的には、剣道における合気の要素は、間合いとタイミングということでは相手との間合いを適切に取ることが大切です。
合気の要素として、この間合いを調整し、相手の攻撃のタイミングに合わせて自分の動きを決定し、相手が打ってくるタイミングを予測して、無駄なく、また無理なく対応することが求められます。
相手の力を感じ取るということでは剣道の合気は、相手の動きや力の方向を読み取り、その力に逆らわず、むしろその力を利用して反応します。
例えば、相手が打突してきた際に、その力を受け流す、または自然に引き出し、有利な位置で反撃することが合気に当たります。
そして、剣道における合気とは、技術だけでなく、精神的な側面も含みます。
心が乱れていると、相手の攻撃を冷静に受け入れることができません。
逆に、心を整えて、中心に気を集中させることが重要です。
これによって、相手の動きに合わせることができ、より効果的に技を出せるようになります。
技を出す際に「自分の体と剣の動き、そして相手の動きが一体となる」ことが理想です。
これは、打突の際に自然な流れで打ち込み、無駄に力で防がず、全身でその流れを受け入れることに繋がります。
自分が考える剣道における「合気」は、単に技術的なものではなく、精神的な調和と技の流れが一体となった総合的なアプローチだと考えられます。
気を合わせることで無理なく優位に立ち、最小の力で最大の効果を得ることができるようになります。
共通する本質と、それぞれの実践
合気道と剣道における「合気」の共通点と相違点を考えてみますと、
それぞれの武道の特性や目的に由来してどちらも「力を使わず、相手の力を利用する」といった原則に基づいていますが、
その実践の方法やアプローチには違いがあるかと思います。
共通点
どちらの武道でも、「合気」は相手の力や動きをうまく受け入れて調和させることが大切です。
無駄な力を使わず、相手のエネルギーを感じ取って合わせること。
技術だけでなく、精神的な集中と内面の安定が重要です。
また、どちらの武道でも自然な動きと流れを大切にするという共通点があります。
相違点
合気柔術は主に素手での技が中心で、接触を通じて関節や体軸を崩す技術が重視されます。
一方剣道は竹刀を使って戦うため、攻防の距離感やスピード、タイミングが大きく異なり、打突による反応と反撃に合気が宿ると感じます。
武道としての本質を支える「合気
最後に自分の考えですが、合気柔術は前重心で腰、指先に気を意識し「緩む」が基本ですが、
剣道においては「ひかがみをいつも張っておけ」と言われるように、右足で誘い、左足で蹴れる後ろ重心と溜めと爆発が強調されます。
この違いは、武道とスポーツの違いでもあると感じます。
剣道がスピードやパワーが優先されスポーツ化されていく中でも、
相手との攻防における合気があるからこそ、剣道が武道としての本質を保っているのかもしれません。
未熟で修行中の身ですが、自分なりの「合気」についての考えを述べさせて頂きました。
國安則光 拝