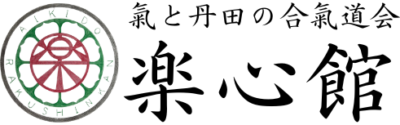頭が固いのか、体が固いのか──合氣道の稽古から見えたこと
1. エアコンの前で実感した「頭を冷やす」
今年の夏はとにかく暑かった。稽古場に着くなり、私はまっすぐエアコンの前に立った。
汗が噴き出して頭に血が上っているとき、冷たい風を浴びると「頭を冷やせ」という言葉が体感としてわかる。
怒りで頭が煮えたぎると、思考も固まり、体まで動かなくなる。じゃあ、頭が固いから体が固いのか。それとも体が固いから頭まで固くなるのか。
そんな問いを抱えたまま、稽古が始まった。
2. 稽古で起きた固さ:体と頭が同時に止まる
受け手が私の手首をがっちりつかんだ。私は自分の思う方向へ動かそうとしたが、まったく動かない。力を入れれば入れるほど、腕も肩も固まってしまう。
「動けない」と思った瞬間、体だけでなく頭も止まる。何をすべきか浮かばず、焦れば焦るほど真っ白になった。
これは、普段の生活でもよくあることだ。喧嘩や議論の場で何か言われても、すぐに返せない。30分後、1時間後になってから「ああ、こう言えばよかった」と考えがまとまる。頭が固まり、言葉が出てこない。稽古で体が固まるのと、全く同じだと感じた。
3. 気づき:相手の力の向きを感じ取り、合わせて流す
そのとき、師から「自分がやりたい方向に行こうとするな」と言われた。
私はずっと「どう動けばいいか」を自分の中に探していた。しかし、視点を変えて「相手はどこに意地を張っているのか」を感じ取ると、固さの向きが見えてきた。そこに力を合わせてみると、体が自然に流れ出す。
頭も同じだ。自分の考えを押し通そうとするほど固まる。逆に、相手がどこに固執しているかを見てみると、不思議と自分の考えも整理される。体と頭はつながっていて、どちらかを緩めればもう一方も動き出すのだと気づいた。
4. 稽古と日常で使える「固さをほどく」ヒント
この気づきは、稽古場だけでなく日常にも役立つ。
- 子どもや部下が言うことを聞かないとき、叱って固めるのではなく「相手はどこに意地を張っているか」を探る。
- 議論の場で言葉が出ないとき、自分の意見を押し出そうとせず「相手が何を大事にしているか」に耳を傾ける。
- 技が止まるときは、自分の体のどこに緊張があるかを観察し、まずそこを緩めてみる。
頭を冷やす、体を緩める、相手を感じる──どれも同じ方向に働く工夫だとわかる。
5. 結論:技の修錬は人間関係にもつながる
結局「頭が固いから体が固いのか」「体が固いから頭が固いのか」という問いには答えが出ない。だが、ひとつ確かなのは、稽古を通してその両方を同時に柔らかくしていけるということだ。
暑い夏にエアコンの前で頭を冷やしたように、稽古の場では体を緩めることで頭も冷静になれる。そうして初めて相手の力を感じ取り、技がかかっていく。
そして、この感覚はそのまま人間関係にもつながる。相手を力で押し通そうとすると関係は固まるが、相手がどこに意地を張っているのかを感じ取ると、自然に会話や関係性も流れ始める。
合氣の技法を修錬することは、技がかかるようになるだけでなく、人と向き合う姿勢を磨き、日常の人間関係を柔らかくする稽古でもあるのだ。
あなたは最近、頭に血が昇って固まってしまった瞬間はありませんか? そのとき、まずどちらを冷やすべきでしょう──頭でしょうか、それとも体でしょうか。